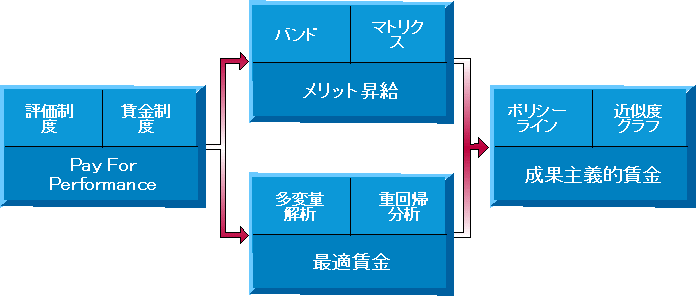
書店やWebサイトで貴方が遭遇する「最適賃金」とは、
60歳定年以降の賃金と在職年金及び雇用保険給付の最適な組み合わせのことでしょう。
しかしUS賃金研究所の最適賃金は行政主導の給付金関連とは無縁のオリジナルです。
現在の賃金(基本給)を任意の決定要素で多変量解析して理論値を計算します。
この段階ではあくまで理論値であり、そのまま最適賃金と見なすことは無理があります。
プロット画面に近似度グラフを出力して、基準線からの残差を確認します。
残差を収束する方向で現在の賃金を調整した結果が、企業内の最適賃金です。
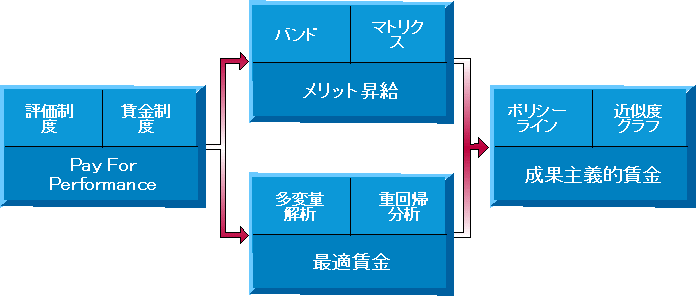
外部労働市場と連結した職種別、熟練度別等級による賃金制度でメリット昇給する場合は、
特に最適賃金などで内部調整する必要はありません。
しかし日本のような企業内賃金決定の条件下では、企業内で調整する必要があります。
 ポリシーラインとは、各々のバンドの中央値を結んで出力するラインです。
ポリシーラインとは、各々のバンドの中央値を結んで出力するラインです。
その中央値が職種または職務別の市場賃金に合わせて設定されているならば、
プロットマークがポリシーラインに収束するのは最適賃金の指標となります。
しかし現状の労働市場では職種または職務別の市場賃金が形成されていない
ことが通常です。
その場合、バンドの中央値は社内的に決定することになります。
例えば、3等級と4等級を合わせて「ミドル」というバンドにしますが、
ミドルの中央値は3等級と4等級の平均値を基準に設定します。
また、基本給が複数の賃金項目で構成されている場合、
バンドは基本給の一部に過ぎないことになります。
このようなとき、ポリシーラインに収束していても最適賃金の指標には
なりません。
ポリシーラインが出力できないとき、または信頼性が低いとき、
自社の最適賃金カーブを出力する必要があります。
その方法として、多変量解析が有効です。
先ず基本給と相関性が高い決定要素を探ります。
その結果、Y=f(α,β,γ)という関数の説明変数が
「職務等級」「勤続年数」「能力評価」であったとします。
そこで多変量解析して最適賃金カーブを出力します。